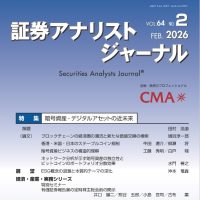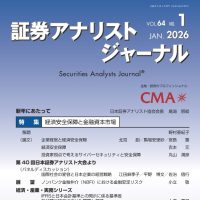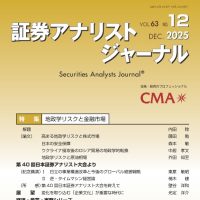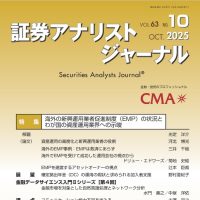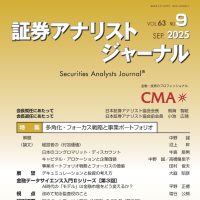(2025年1月号分から「クラブ・インベストライフ」にて本記事を見ていただいています。下の方に、はじめてこの記事を見ていただいた方向けの説明がありますのでご覧ください!)
(2025年1月号分から「クラブ・インベストライフ」にて本記事を見ていただいています。下の方に、はじめてこの記事を見ていただいた方向けの説明がありますのでご覧ください!)
やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『企業情報開示再考―統合報告書の位置づけと開示体系の再構築―』という特集です。
「中野ゼミ」においても統合報告書について研究をしているので、大変興味深いテーマです!
さて、解題に書いてあるのですが、企業情報開示について俯瞰的に見ていくと、その開示の種類の多さに問題意識を覚えます。
①統合報告書の他に、制度として開示が要請されている、②有価証券報告書、③コーポレートガバナンス報告書、④株主総会招集通知、⑤決算短信、そして任意としての開示では、⑥サステナビリティ報告書、⑦決算補足資料といったものがあります。
そして、受け取り側の意見として、①内容が重複している、②タイミングが遅い、③自由に記述されていて比較しにくい、④一つにまとめてほしい、といった問題意識があるようです。
企業サイド(情報開示サイド)と投資家サイド(受け取りサイド)、両サイドからの主張がありそうです。
それでは、読み進めていきたいと思います!
1本目は座談会形式、『企業情報開示再考―統合報告書の位置づけと開示体系の再構築―(古布薫/谷口岩昭/八田浩一/北川哲雄氏)』です。
中外製薬CFOの谷口岩昭さん、東京エレクトロンIR室の八田浩一さんが登場、企業サイドからの意見が述べられているという貴重な座談会です。
企業情報開示の歴史を肌で感じている2人のご担当者のリアルな意見がありました。
東京エレクトロン・八田さんはIR室に異動になったのが7年前だそうですが、当時(2017-8年でしょうか)は統合報告書を発行していなかったそうです。2020年に入ったころに流れが変わってきたと言っています。
最初に統合報告書を発行したときは、サステナビリティ統括部(当時のCSR推進室)が中心となって進めていたが、今では様々な部署を巻き込んだビッグプロジェクトになっているそうで、最初の統合報告書発行から数年で量と質の両面で大きな進化を遂げてきたことを感じさせます。
中外製薬・谷口さんは、序盤の議論で「報告書の種類が過剰気味だという問題意識がある」と述べ、終盤の議論で「一丁目一番地はone report化だろう」と述べています。企業情報開示の内容の重複については、この後に紹介する論文でも大いに議論されていますので、改めてどのような進化が適切かを考えたいところです。
さて、これまでの出来事を振り返ってみると、投資家は「企業価値の分析」という旗印を掲げ、わりと好き勝手にいろいろな声を出してきたように思います。そこに、企業が情報開示をするためのコスト・マンパワーを慮る感じはなく、企業側は(大変だと思いながらも)出来るだけ応えてきました。
投資家サイドに企業サイドをリスペクトする気持ちがしっかりとあって、声の出し方を工夫すれば良かったのにと思います。
また、投資家サイドと企業サイドを調整する仕組みがあれば良かったのにとも思います。
今、歩み寄るべき時期が来ているのではないでしょうか。
2本目の論文は『わが国企業情報開示の課題とあるべき方向性―有価証券報告書の株主総会前開示の実現に向けて―(熊谷五郎氏)』です。
本論文では、企業情報開示の国際動向についてが書かれており、参考になりました。
記述情報重視の傾向が世界的な潮流になっているようです。ユニバーサル・アセットオーナーはインデックスのリターンそのものを引き上げることを目指していて、その結果、重視されるようになったのが企業とのエンゲージメントであり、エンゲージメントのためには、企業の経営方針、事業戦略、ビジネスモデル棟の理解が欠かせないとして、記述情報が重視されているという話の流れです。
そんな記述情報の中でも、サステナビリティ情報が国際的に重視されていて、特に欧州が先行しているとしています。
米国がトランプ大統領による政権になり、それらの開示がステップバックするかもしれない中、欧州についていくべきか?という議論はありそうですが、今後も国際動向をしっかりとウォッチして、適宜対応していく必要があるでしょう。
対応していく中で、任意開示で比較的自由な記述が可能である「統合報告書」はサステナビリティ情報など、記述情報の開示をするにあたり、良いプラットフォームであると言えます。
一方で、2023年3月期から、有価証券報告書においてサステナビリティ情報の開示が上場企業に義務付けられました。
任意開示で自由な記述が可能である統合報告書と、制度開示で記述形式がある程度定められている有価証券報告書で、重複する内容をどのように書き分けるべきか、企業は悩む(混乱する)のではないでしょうか?
投資家からの声があり、金融証券取引法による義務化があり・・・。企業の情報開示ご担当者の方々は大変だとつくづく思います。
3本目の論文は『わが国の企業情報開示体系の再構築に向けて―経済産業省懇談会中間報告を踏まえて―(松山将之氏)』です。
ここまでの座談会+2本の論文で、「日本の企業情報開示はカオスな状況だ!」と感じましたが、カオスな状況を解消すべく、経済産業省が動いているのが分かるのが本論文です。
まず知っておくべきこととして、2024年4月に「企業情報開示のあり方に関する懇談会」が立ち上げられ、2024年6月に「企業情報開示のあり方に関する懇談会 課題と今後の方向性(中間報告)」がリリースされました。内容を理解するためには、これらのリンクを見ていただくのが一番ですが、こちらでもザックリ書いてみようと思います。
中間報告の一番大きなポイントとしては、企業情報開示の目指す姿について具体的に案が2つ挙げられているところかと思います。
1つ目は、これまでの法定開示を1つの法定開示書類に集約し、統合報告書は任意開示の役割を維持させるという案です。
もう1つは、法定開示の枠組みを大きくして、今の統合報告書にあるビジネスモデルや価値創造プロセスといったものを入れ込んでしまい、任意開示はサポート的な役割にするという案です。
後者を目指すべき意見が比較的多かったそうですが、著者はその後の丁寧な議論の中で、実現可能性を鑑みると前者なのではなかろうかと主張しています。
4本目の論文は『わが国の企業情報開示における統合報告書の役割と課題(奈良沙織氏)』です。
本論文は、基本的な知識が身に付く、今回であれば統合報告書の基本についてがよく分かる、証券アナリストジャーナル的には1本目の論文に出てくるような論文でした。
まず、ますます重要になっていく非財務情報ですが、その背景として、
①企業価値創造の源泉が有形資産から無形資産にシフトしてきている
②ショートターミズムの反省から、長期的な企業価値創造を考えるための情報ニーズがある
③ESG投資やサステナブル投資を行うにあたっての情報ニーズがある
という3点が書かれています。
これらの情報は財務情報発信のフォーマットでは開示しにくいものであり、財務情報と非財務情報をミックスして発信できる統合報告書(またはアニュアルレポート)が適しているということになります。
そして、統合報告書を作成するにあたって参照する、IIRCの「国際統合報告フレームワーク」について紹介されています。
このフレームワークでは、他の開示であまり記述しない項目として、「ビジネスモデル」、「戦略と資源配分」、「見通し」といったものがあり、これらが上記の①②③に呼応していることが分かります。
また、統合報告書にはいくつかのなユニークな開示がありますが、有形・無形の資産をインプットとして、どういった企業活動からアウトプット、アウトカムが生まれていくかを示す「価値創造プロセス」のビジュアライゼーションはまさに「ならではの開示」であり、企業の理解に役立っていると(私は)思います。
統合報告書を読んだことの無い方は、ぜひ興味のある企業のホームページに行っていただいて、統合報告書をダウンロードして、価値創造プロセスなどを体感してみてください!
上記の他には、「統合報告書による開示を行うメリット」、「統合報告書を含む企業開示の課題」といった章があり、それぞれ、理解を深めることができました。
初学者でも読みやすく、情報がしっかりとまとまっていて、ありがたい論文でした!感謝!
読了後のひとこと
今月号の証券アナリストジャーナルは、『企業情報開示再考―統合報告書の位置づけと開示体系の再構築―』という特集でした。
比較的小規模の上場企業は情報開示の要求にコスト面・マンパワー面の制約からどうしても応えられないところがありますし、コスト面・マンパワー面で何とかなる規模の上場企業にとっても「統合報告書を作成する動機は、他社さんがやっているから」といった後ろ向きな理由で情報開示していたりします。
「企業価値向上に結び付く情報開示」をしっかりと考えなければいけません。
松山論文にある、法定開示を集約していくというのは実現可能性があり、任意開示の整理は後回しになりますが、確実に一歩進むことが出来る良い方向性だと思いました。
ちょっと横道に逸れますが、IPOでの情報開示も同様に集約していけるのではと思います。
IPOでの情報開示の現状は、証券情報、企業情報、提出会社の保証会社等の情報、特別情報、株式公開情報といった項目が、有価証券報告書Ⅰの部、有価証券届出書、目論見書という3書類に載っていたり載っていなかったりという状況です。これが集約されるといいなぁと思っている投資家サイドや企業サイドの方は多いのではないでしょうか・・・。
何はともあれですが、投資家サイドと企業サイドの歩み寄りが行われて、資本市場全体としての価値が向上していく流れになって欲しいと切に思いました。
ということで、今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!
はじめてこの記事を見ていただいた方に
はじめまして!金融教育家のやすべえと申します。
私は、大学卒業後、証券会社3社にて金融商品のトレーダーとして20年近く勤務し、2018年から金融教育家として活動を開始しました。
詳しい説明はコチラにありますので、ぜひご覧くださいませ!
「証券アナリストジャーナル」とは、日本証券アナリスト協会が発行する会員向け月刊機関誌です。
私は、2002年に証券アナリスト検定会員となり、本誌を読み始めまして、2017年から本ブログに読んだ感想をしたためるようになりました。
「備忘録」でもあり、「書きなぐり」に近いものです。その点、ご容赦頂ければ幸いです。
ただ、証券アナリストジャーナルに寄稿してくださる方に敬意を持つこと、ブログの読者に誤解を与えずに私の思っていることをお伝えしようと心に留めながら書いています。
また、タイトル名と著者名のリンクをクリックすると日本証券アナリスト協会のサイトにジャンプし、本文の1ページ目を無料で読むことが可能です。有料で全文を購入することも可能です。
はじめましての皆さま、これまでも読んでいただいている皆様、今後とも本ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
Facebookの告知ページがありますので、フォローやいいね!をしていただけますと、ブックマーク代わりになります。
証券アナリストジャーナルに関するものや、その他の私のアウトプットについての告知を追うことが可能です!
感謝!
- 投稿タグ
- 証券アナリストジャーナル