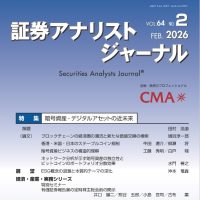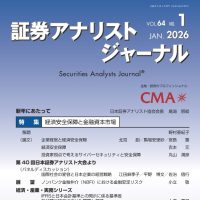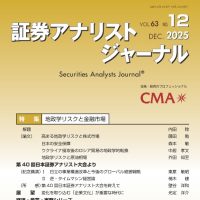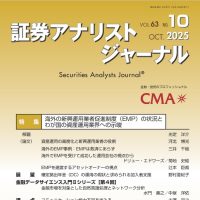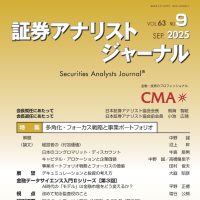やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『インドの金融資本市場―課題と新展開―』という特集です。
やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『インドの金融資本市場―課題と新展開―』という特集です。
「BRICs」という造語が出来たのは2001年のことなんだそうです。
ブラジル、ロシア、インド、中国の4か国、または、南アフリカを加えた5か国を束ねた言葉ですが、今振り返ってみると、それぞれの国がそれぞれの道を進んでいます。いやはや、ほんまに、それぞれの道を進んでいます。
さて、本誌の内容ですが、インドの金融資本市場について大いに深堀りしています。
インドの金融資本市場に関する4名の論考が一気に読める機会はなかなか無いと思うので、ありがたいですし、良い知見が得られる予感がします。
ということで、今月号も楽しみながら読み進めたいと思います!
1本目の論文は『経済成長下のインドの金融システム構造(西尾圭一郎氏)』です。
インドは銀行システムの規模に対する証券市場の規模が大きいのですが、その理由を説明してくれています。
私はこの論文を読むまで、その事実を知りませんでした。おそらく、インド株に投資している人でその事実を知っている割合はかなり小さいのではないでしょうか?ま、知っていようがいまいが、投資パフォーマンスに変わりはないのですが・・・。
かつてのインドは、政府の財政に従属するようなシステムであったようです。
①法的流動性比率(SLR, Statutory Liquidity Ratio)という、預金のX%を上限に国債などを保有するという規制があり、1990年には38.5%だったそうです。今は18%に下がっていますが、強制的に国債を保有させるような規制で、なかなかビックリです。
②預金準備率は、色々な国にありますけれども、預金のX%を中央銀行に預けるという制度で、1990年には15%だったそうです。(今は4%。)
③優先部門貸出規制(Priority Sector Lending)という、貸し出しの一定比率(4割)を農業や零細企業などの優先部門向けに貸し出す規制があります。こちらも国の政策として分かりやすいものではありますがビックリです。
上記より、例えば1990年に100万ルピーの預金が入ったとすると、38.5万ルピーはインド国債を購入し、18万ルピーは中央銀行に預け、残った43.5万ルピーのうち、17.4万ルピーは優先部門に貸し出すので、残りの26.1万ルピーしか自由に貸し出しが行えないという事になります。
これでは銀行の商売としては厳しいのではないでしょうか?
ちなみに、1991年の経済自由化が大きな転換点となり、変化が進んでいます。
他に、デジタリゼーションにおいて最も注目される、「Unified Payments Interface」というキャッシュレス決済システムが紹介されたり、それに付随するような形で2016年に高額紙幣が廃止されたといったことも書かれています。
ほぼ何も知らなかったインド金融システムですが、ある程度の知識武装を進めることができました!
2本目の論文は『海外投資家の注目を集めるインド資本市場―投資促進策と国際金融特区の創設を中心に―(北野陽平氏)』です。
この論文では、インドへの投資促進策と国際金融特区についてがよく分かります!
前者「インドへの投資促進策」に関することですが、FPI(Foreign Portfolio Investor)という、株式市場や債券市場等への投資を行う外国ポートフォリオ投資家についての投資が増えています。規模感としては2025年5月末で78兆ルピーといったところです。また規模はFPIより小さくなり、4-5兆ルピー程度ですが、FDI(Foreign Direct Investment)という、上場企業の発行済み株式10%以上の取得や非上場企業等への投資を行う外国直接投資があります。
後者「国際金融特区」においては、GIFTシティ(Gujarat International Finance Tec-City)という国際金融特区が2015年に創設され、海外の金融機関の進出が進んでいるとありました。
インド資本市場はまだまだ発展の途中であり、インド株への投資妙味を感じるようなペーパーでした。
何はともあれですが、投資は自己責任で!
3本目の論文は『世界でのイノベーション震源地および有望投資先としてのインド・スタートアップ生態系(江藤宗彦氏)』です。
インドのスタートアップ生態系について書かれた論文です。なかなか知ることが難しいエリアだと思うので、僕にとって非常に価値が高く、とても有難く感じました。
インドのユニコーン企業は2014年には4社しかなかったのですが、2025年6月までには113社まで増大したそうです。
113社は米国と中国に次ぐ世界3番目の数だそうで、日本の8社と比べるとその多さに圧倒されますが、何かとんでもないことが起こっていると容易に想像できます。
その背景として何があったのか?というところが非常に気になりますが、著者は、「デジタル化とスタートアップ発展には強い関連性がある」とし、先行論文の引用として、「デジタル政策とスタートアップ支援策が相乗効果を生み出す」とも指摘しています。
1本目の論文で出てきた「Unified Payments Interface」も大きな効果があったという記述もありました。
デジタル化の流れをしっかりつかんで、ユニコーン企業が続々と生まれていることが分かりました!
4本目の論文は『インドの株式市場:リスクオフ局面におけるグローバルショックの影響(大野早苗氏)』です。
論文のタイトルにある「リスクオフ局面におけるグローバルショックの影響」についても、新興国にありがちな海外投資の大きな満ち潮と引き潮を考えていて興味深いですが、その前段にある「非居住者が保有する新興国の株式の時価総額(上位5カ国)」というのが、はっとするものでした。
日本の居住者が保有する各国の時価総額で、ここ3年程度でインド株が2倍程度になり、新興国の中でトップとなっているんです。
10年前には、中国→韓国→インドという順番だったのが、2024年には、インド→台湾→中国といった順番に変わっています。
日本の海外投資のリアルな一面を見ることができました。
読了後のひとこと
今月号の証券アナリストジャーナルは、『インドの金融資本市場―課題と新展開―』という特集でした。
国別の投資を考える際に、どの国にも長所と短所があることを認識して投資を実行しますが、今回の特集でインドへの投資に関する長所と短所がよく分かりました。
経済の高い成長と規制緩和が進むところは非常に強い長所と感じます。一方で、通貨の安定性は新興国では避けられませんが短所ではあります。しかし、先進国の通貨が盤石である時代でも無いですし、資産分散の一方法である通貨分散で乗り越えられるのかもしれません。
今回のインドの金融資本市場に限らず、どんなときも「データや事実」をしっかりと見て判断していくことが大事ですが、インドに関する様々なデータや事実を目の当たりにして、確からしい答えが自分なりに見えてきた気がします。
ということで、今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!
はじめてこの記事を見ていただいた方に
はじめまして!金融教育家のやすべえと申します。
私は、大学卒業後、証券会社3社にて金融商品のトレーダーとして20年近く勤務し、2018年から金融教育家として活動を開始しました。
詳しい説明はコチラにありますので、ぜひご覧くださいませ!
「証券アナリストジャーナル」とは、日本証券アナリスト協会が発行する会員向け月刊機関誌です。
私は、2002年に証券アナリスト検定会員となり、本誌を読み始めまして、2017年から本ブログに読んだ感想をしたためるようになりました。
「備忘録」でもあり、「書きなぐり」に近いものです。その点、ご容赦頂ければ幸いです。
ただ、証券アナリストジャーナルに寄稿してくださる方に敬意を持つこと、ブログの読者に誤解を与えずに私の思っていることをお伝えしようと心に留めながら書いています。
また、タイトル名と著者名のリンクをクリックすると日本証券アナリスト協会のサイトにジャンプし、本文の1ページ目を無料で読むことが可能です。有料で全文を購入することも可能です。
はじめましての皆さま、これまでも読んでいただいている皆様、今後とも本ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
Facebookの告知ページがありますので、フォローやいいね!をしていただけますと、ブックマーク代わりになります。
証券アナリストジャーナルに関するものや、その他の私のアウトプットについての告知を追うことが可能です!
ありがとうございます!
- 投稿タグ
- 証券アナリストジャーナル