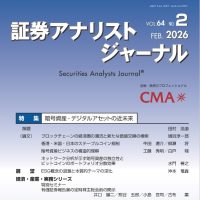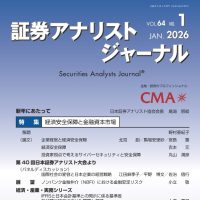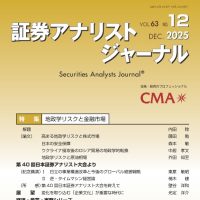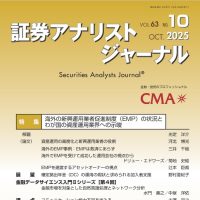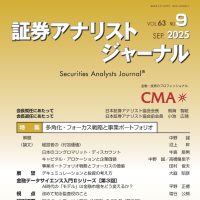(2025年1月号分から「クラブ・インベストライフ」にて本記事を見ていただいています。下の方に、はじめてこの記事を見ていただいた方向けの説明がありますのでご覧ください!)
(2025年1月号分から「クラブ・インベストライフ」にて本記事を見ていただいています。下の方に、はじめてこの記事を見ていただいた方向けの説明がありますのでご覧ください!)
やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『エンゲージメントとスチュワードシップ活動の今』という特集です。
コーポレートガバナンスコードや、スチュワードシップコードという言葉はわりと新しい言葉である気がしますが、10年ほど前に出来たものだそうです。
時が経つのは早いものですが、これら2つのコード(「ダブルコード」と呼んでいた時期もありました・・・)の存在で、企業価値の向上に向けた活動がしっかりとした指針の下で行われてきたのではないでしょうか。
ちなみに、本ブログ読者にはおそらく釈迦に説法ですが・・・。
コーポレートガバナンスコードは、上場企業を対象とした、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話、それぞれについての基本原則を記したもので東証が定めているものです。
また、スチュワードシップコードは、機関投資家を対象とした、責任ある投資と対話を促すための諸原則を記したもので金融庁が定めているものです。
ということで、今月号も楽しく読み進めていきたいと思います!
また、過去の関連する特集としては2023年1月号「人的資本経営とエンゲージメント」がありました。その時のブログ記事はコチラです
1本目の論文は『スチュワードシップ・コードの10年―これまで、そしてこれから―(円谷昭一氏)』です。
本論文の序盤では、スチュワードシップコード策定(2014年2月)からの10年を振り返っています。著者は国内機関投資家の「やるべきことが急増した」と書いていて、具体的に、①議決権行使の厳格化、②投資先との対話、③責任投資レポートの発行、④アセットオーナーへの説明、⑤ESG・サステナビリティへの対応、それぞれをやるべきこととして列挙しています。
そして、それらやるべきことをやった結果、その働きは国際的に評価されているとACGA(Asian Corporate Governance Association)の「CG Watch」の結果を引用して紹介しています。
次に、エンゲージメントについて考えています。ISS(Institutional Shareholder Services)の様々なレベルのエンゲージメントという図が分かりやすく、議決権行使、手紙の送付、面談、株主提案、Vote No キャンペーン、プロキシーファイト、といった6つのエンゲージメント手段を紹介しています。エンゲージメントは着実に進んでいるようです。
後半は、議決権行使についてが書かれています。2017年のスチュワードシップコードの見直しで議決権行使結果の個別開示についてが進みました。今では主要機関投資家のほとんどがエクセルベースで株主総会での行使結果を開示していますが、この動きはここ数年の進歩ということになります。議決権行使で反対票を投じることが増えたように感じます。
そして、「議決権行使に対する形式的な基準」と「対話によって理解を深める行為」が一見矛盾するのではないかという議論が興味深いです。
議決権行使というのは総合的に判断するべきものですが、形式的に判断すると思いもよらない結論を導きかねないというものです。例えば、企業価値向上に際してとても優秀である代表取締役がサステナビリティの開示やジェンダーダイバーシティの形式的基準によって総会で取締役就任を否決されるといったことが起こってしまうといった話です。
この辺りの話は最終盤の著者の私見のところにも書いてあり、思わず頷きながら読み進めました。
2本目の論文は『機関投資家の議決権行使基準と行使行動の変容(脇山卓也氏)』です。
機関投資家の議決権行使について、時系列、議案の項目別で、くわしく書かれています。ぜひ論文をチェックしてみてください!
時系列については、2018年、2021年、2024年の推移が出ているのですが、3年ごとという短いスパンでもかなり変化していることが分かります。
議案の項目については、剰余金処分議案、取締役選任議案、株主提案について細かく書かれています。
私が一番興味深く見たのは、株主提案の基準の推移についてです、
トリッキーな提案も時に見かける株主提案ですが、機関投資家は何らかの基準を設け、準備しています。
時系列の最初に出てくる2018年では「定性的な基準」を整備し、最近の2024年では「個別具体的な株主提案に対応できる基準」を整備しているとデータは言っています。
後半には「反対比率の推移」についてのデータがあり、こちらも興味深く見ることが出来ました。
3本目の論文は『アクティビスト・ファンドの現状と学術研究からみた投資先企業の株価、業績への影響(鈴木一功氏)』です。
「投資家の目線」で最も興味深かったのが本論文です。
アブストラクトに、アクティビストファンドの活動によってリターンや業績がどうなったのが書いてあります。
著者は、アクティビストファンドの活動を、第1波(2001-2009)と第2波(2017-)に分け、リターンは第1波、第2波、ともに有意にプラスであり、企業業績に関しては第1波ではマイナス、第2波では改善したという明確なデータはないと分析しています。
図表のデータが本当に興味深くて、全てを書けないのが残念ですが、2つだけかいつまんで紹介します。
①アクティビストのターゲット企業数は大量保有報告書での5%以上保有の社数でいうと、2019社に100社を超え、2024年では188社ある
②アクティビストファンドによる株主提案を受領した社数は、2022年にそれまでの30社以下から大幅に増加し50社を超え、2023年には70社を超え、2024年も60‐70社ある
すごく興味深い論文でした。ありがとうございます。
4本目の論文は『英国・米国のコーポレートガバナンスの歴史とわが国への示唆(林順一氏)』です。
海外のコーポレートガバナンスの歴史を知ることが出来る貴重な論文でした。
英国のコーポレートガバナンスの本格的な議論は1992年のキャドバリー報告書に始まるそうです。
え?あのお菓子のキャドバリーが・・・?と思いましたが、Wikipedia(Cadbury Report)によればSir Adrian Cadburyさんというキャドバリーの会長が委員会の委員長を務め・・・ってやっぱりお菓子のキャドバリーとつながりはあったんですが、何はともあれ、その報告書によって始まったそうです。
我が国のスチュワードシップコードは2012年版の英国のスチュワードシップコードを参考に作成されたとありました。NISAについても英国のISAを参考にしたと思いますし、進んでいる国から学ぶことは本当に大事だなと思います。
米国のコーポレートガバナンスの歴史については、1943年のジョンソン・エンド・ジョンソンのOur Credo(日本版のOur Credoはこちら)についてが書かれていました。
このような考え方が全ての企業で取られていたわけではないでしょうが、ビジネスラウンド・テーブルでは、会社の目的について1982年、1997年、2019年に声明を出していて、2019年の声明について著者の和文を引用しますと、「われわれ経営者は、われわれの会社、地域社会、そしてわが国の将来にわたる繁栄のために、すべてのステークホルダーに対して価値を提供することにコミットする」とあります。
投資家だけでなく、すべてのステークホルダーに目を向けることが、ますます大事になっている昨今です。
読了後のひとこと
今月号の証券アナリストジャーナルは、『エンゲージメントとスチュワードシップ活動の今』という特集でした。
いわゆる「ダブルコード」については、上場企業がコーポレートガバナンスコードに則って施策を行い、機関投資家がスチュワードシップコードに則って施策を行うという、「2つのコミュニケーションプロセスが1+1=2以上の価値を生む」という、理想形のようなものを目指していたと考えています。しかし、上場企業は施策を行うコスト負担を誰に請求できるわけでもなく骨折り損だという意見があったり、機関投資家は実効性のある施策が出来ているのかという課題があったり、理想形にたどり着くことができるのか、今も両者、悩みながら進んでいるという状況ではないでしょうか。
本特集にて、その答えは見えませんでした。
小さな上場企業は相対的に大きなコスト負担を背負いつづけ、その恩恵を機関投資家から受けることはほぼほぼありません。
「本当に両者Win-Winな理想形はあるのだろうか?」
そんなことを考えた今月の特集でした。
ということで、今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!
はじめてこの記事を見ていただいた方に
はじめまして!金融教育家のやすべえと申します。
私は、大学卒業後、証券会社3社にて金融商品のトレーダーとして20年近く勤務し、2018年から金融教育家として活動を開始しました。
詳しい説明はコチラにありますので、ぜひご覧くださいませ!
「証券アナリストジャーナル」とは、日本証券アナリスト協会が発行する会員向け月刊機関誌です。
私は、2002年に証券アナリスト検定会員となり、本誌を読み始めまして、2017年から本ブログに読んだ感想をしたためるようになりました。
「備忘録」でもあり、「書きなぐり」に近いものです。その点、ご容赦頂ければ幸いです。
ただ、証券アナリストジャーナルに寄稿してくださる方に敬意を持つこと、ブログの読者に誤解を与えずに私の思っていることをお伝えしようと心に留めながら書いています。
また、タイトル名と著者名のリンクをクリックすると日本証券アナリスト協会のサイトにジャンプし、本文の1ページ目を無料で読むことが可能です。有料で全文を購入することも可能です。
はじめましての皆さま、これまでも読んでいただいている皆様、今後とも本ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
Facebookの告知ページがありますので、フォローやいいね!をしていただけますと、ブックマーク代わりになります。
証券アナリストジャーナルに関するものや、その他の私のアウトプットについての告知を追うことが可能です!
ありがとうございます!
- 投稿タグ
- 証券アナリストジャーナル