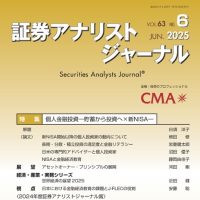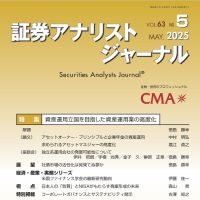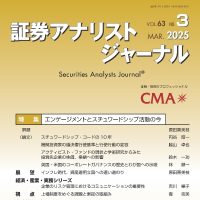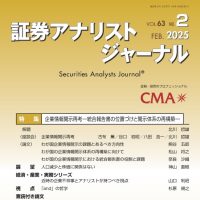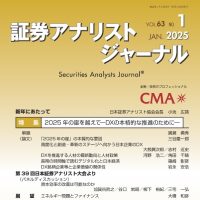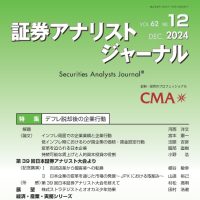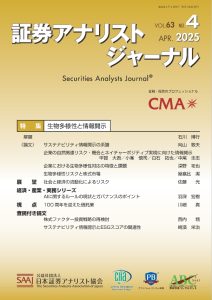 やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『生物多様性と情報開示』という特集です。
やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『生物多様性と情報開示』という特集です。
「リターン」の1軸だけで考えていた投資の時代がありました。
1952年にハリー・マーコウィッツによって発表された論文からと言われていますが、現代ポートフォリオ理論の発展などで、「リスクとリターン」の2軸で考える投資の時代になり、インデックス投資を続けておけばリスクを押さえて平均的なリターンが得られるとの意見が主流になりました。
今は「リスクとリターンと社会的インパクト」の3軸で考える投資の時代への移行期でしょうか?
ここ数年のインデックス投資の爆発的な盛り上がりは、「リスクとリターン」の2軸で考える時代の終焉を示唆しているかもしれません。(完全に私の邪推です!笑)
誰にもその答えは分かりませんが、気候変動や今回のテーマである生物多様性について考えることは、「リスクとリターンと社会的インパクト」の3軸で考える時代に対する予習になるでしょう。
何はともあれですが、今月号も楽しく読み進めていきたいと思います!
また、過去の関連する特集としては2019年4月号「地球温暖化と株式市場」がありました。
今も不勉強で、気が向けば知見を積むだけの私ですが、5年前の私の書きっぷり、実にお恥ずかしい限りです・・・。
1本目の論文は『サステナビリティ情報開示の系譜―生物多様性への道―(向山敦夫氏)』です。
本論文では、サステナビリティ情報開示の歴史が載っています。今後の展開を考えるうえで非常に有益だと思いました。
①公害問題や2度のオイルショックを経験した1960年代から70年代は、企業を批判的にとらえる視点で「企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)」が議論された時期
②1980年代はレーガノミクスやサッチャリズムにみられる規制緩和・自由競争・市場至上主義の揺り戻しを経験
③1970年代に中心であった社会の関心事は「従業員」から、1990年代に入って「環境」へと移行し、世界的にも企業は環境情報の開示やその媒体である環境報告書の作成へと進んでいった
④(Global Reporting Initiativeについて、)初版ガイドライン(G1)を2000年に発行して以降、G2(2002年)、G3(2006年)、G3.1(2011年)、G4(2013年)、GRI Standards(2016年)と改訂され、さらに2021年に共通スタンダードの改訂版(2021年)ガイドラインを公表
といった内容です。(①~④、(Global Reporting Initiativeについて、)は私が追記しましたが、その他は引用)
終盤に、サステナビリティ情報を開示する目的について書かれていて、具体的には、社会的アカウンタビリティを論拠としていたが、ESG投資の波やPRIによって、財務資本提供者への情報提供に変化したとあります。
筆者はこの変化に対して、「良い意味でも悪い意味でも」と書いており、疑問を投げかけています。
この疑問をさらに深めるような文脈で、Dechow, P. M. [2023] “Understanding the Sustainability Reporting Landscape and Research Opportunities in Accounting”という論文より、16行分という長い引用をしています。その中に「私たちは本当に、持続可能性が企業価値にどのような影響を与えるかに焦点を当てるべきなのだろうか?サステナビリティ報告の意義は、社会を助け、地球を救うことにあるのではないだろうか?」という文章があり、何と表現すればよいでしょうか、とてつもなく大きな「ボタンの掛け違い」の可能性に筆者はDechowと共に警鐘を鳴らしているのではないかと私は感じました。
2本目の論文は『企業の自然関連リスク・機会とネイチャーポジティブ実現に向けた情報開示(甲賀大吾/小峯慎司/白石拓也/中尾圭志氏)』です。
「ネイチャーポジティブ」というパワーワードを使い、自然資本や生物多様性に良い影響を与えようと考えていることがよく分かる論文でした。
ただ、「ネイチャーポジティブ実現に向けて、各国でルールメイキングが活発になっており」といった記述や、「2030年にはネイチャーポジティブ経済への移行により、(中略)年間10.1兆ドル規模のビジネス機会と、3億9500万人の雇用創出が見込まれている」といった記述に、権力争いや、正しさを主張する裏にある意図や、マネタイズ志向による本来の目的からの歪みが生じる可能性が感じられました。
「DO GOOD」はミクロ、またはミクロから始まるアプローチによって生まれるもので、マクロのアプローチで押し付けることは出来ないと思ってしまう今日この頃です。
3本目の論文は『企業における生物多様性対応の特徴と課題―気候変動との関係性を中心に―(深野祐也氏)』です。
本論文は、深野祐也さんという、園芸学研究員の准教授で専門が生態学という、証券アナリストジャーナルにはなかなか登場していただけないような方が書いています。
読後の感想としては、本当に素晴らしい論考だと思いました。ぜひ一読していただけたらと思います。
論文の章建て(10章)がユニークで、『はじめに』、『生物多様性と企業は対立していた』、『脱炭素の「次」だが、脱炭素の「隣」ではない』、『測定が困難である』、『単一の指標が無い』、『局所的な課題の集合である』、『ビジネスとの接点が多岐にわたる』、『愛がすごい』、『脱炭素とのトレードオフとシナジー』、『結論と将来の展望』となっています。どの章に興味が湧きますか?
『局所的な課題の集合である』の章では、「気候変動は地球全体を一つのシステムとして捉える課題なのに対して、生命多様性の劣化は各地域で起きているローカルな課題の集合体である」と述べています。2本目の論文を読んで『「DO GOOD」はミクロ、またはミクロから始まるアプローチによって生まれるもの』と思ったことを後押しされた気がします。
また、『愛がすごい』の章では、「どんなに気候変動に強い関心がある人でも、ボランティアで、あるいは私財を投じて、脱炭素活動に勤しむ人は、ほとんどいないだろう。しかし、生物多様性には、そのような活動をする人がたくさんいる。」と述べています。気候変動に対してルールを作りルールを守りなさいと言うよりも、生物多様性への愛のほうが強い影響力を持っていて、おそらく筆者はここに大きな可能性を感じているのではないでしょうか。
結びには、「生物多様性対応を一つの契機として、企業活動が人間社会を含む地球環境システムの中にあるという枠組みを持つことで、頑健で持続的な企業静養に向けた移行が達成されるだろう。」と書いています。
4本目の論文は『生物多様性リスクと株式市場―初期の文献レビュー―(屋嘉比潔氏)』です。
こちらの論文は、生物多様性リスクが市場や企業に与える影響について研究された論文のリスト的な役割になっています。
さて、AIに「生物多様性リスクと株式市場の関係性に関する英語の先行研究のリストアップと5つのカテゴリへの分類」をお願いしたら、こんな回答になりました。
1. 企業レベルのリスクと株式リターン
中国市場の分析: 企業の生物多様性リスク露出が株式リターンと負の相関を示し、機関投資家の保有率が低い企業で影響が顕著。
フランスの研究: 生物多様性への依存度が高い企業(農業など)で期待リターンが低下し、市場が将来リスクを先取りしていることを示唆。2. リスクプレミアムと資金調達コスト
スイスの研究: 生物多様性フットプリントが1標準偏差増加するごとに、月次リスクプレミアムが23ベーシスポイント上昇(年率2.8%相当)。
業種間比較: 小売・卸売、紙・林業、食品業界でリスクプレミアムが高く、半導体・ソフトウェア業界で低い。3. グローバル市場での価格付け
117ヵ国2万銘柄の分析: 2021年クンミン宣言後、米国で「生物多様性ベータ」が顕著に上昇し、気候リスクとは独立した因子であることを確認。
ヘッジング戦略の有効性: 低リスク業種をロング、高リスク業種をショートしたポートフォリオが、生物多様性ニュース指数と連動。4. システミックリスクと経済影響
ECBのモデル: 生物多様性喪失がCDSスプレッドに影響し、生態系が脆弱な国の債務デフォルトリスクが上昇。
OECDの推計: 金融機関の資産の35-54%が生態系サービスに依存し、7-10%のGDP損失リスクを指摘。5. 国際規制と市場反応
クンミン宣言の影響: 宣言後3日間で高リスク企業の株価が1.18%下落し、規制リスクの価格付けが加速。
モントリオール協定: 生物多様性保護が不十分な国で土地依存企業の株価反応が顕著にネガティブ。これらの研究は、生物多様性リスクが企業評価・資金調達コスト・システミックリスクに影響し、気候変動とは異なる独立したリスク因子として認識されつつあることを示唆しています。特に2021年以降の国際合意を契機に、市場の価格付けメカニズムが変化している点が特徴的です。
筆者とは違う切り口ですが、筆者が引用した研究と同じものをAIも採り上げていたり、なかなか興味深いテストになりました。
読了後のひとこと
今月号の証券アナリストジャーナルは、『生物多様性と情報開示』という特集でした。
「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる」という言葉は、カナダの精神科医であるエリック・バーンさんの言葉だそうです。
部分最適と全体最適が違うことをしっかりと認識し、自分が全体最適が正しいと思えばそれに即した行動する中で、他人を巻き込んでいくようなムーブメントが求められます。
その答えは「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」や「TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)」にあるでしょうか?
私にその答えは見えませんが、、、今後も否定的ではなく建設的に考えていきたいと思います。
ということで、今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!
はじめてこの記事を見ていただいた方に
はじめまして!金融教育家のやすべえと申します。
私は、大学卒業後、証券会社3社にて金融商品のトレーダーとして20年近く勤務し、2018年から金融教育家として活動を開始しました。
詳しい説明はコチラにありますので、ぜひご覧くださいませ!
「証券アナリストジャーナル」とは、日本証券アナリスト協会が発行する会員向け月刊機関誌です。
私は、2002年に証券アナリスト検定会員となり、本誌を読み始めまして、2017年から本ブログに読んだ感想をしたためるようになりました。
「備忘録」でもあり、「書きなぐり」に近いものです。その点、ご容赦頂ければ幸いです。
ただ、証券アナリストジャーナルに寄稿してくださる方に敬意を持つこと、ブログの読者に誤解を与えずに私の思っていることをお伝えしようと心に留めながら書いています。
また、タイトル名と著者名のリンクをクリックすると日本証券アナリスト協会のサイトにジャンプし、本文の1ページ目を無料で読むことが可能です。有料で全文を購入することも可能です。
はじめましての皆さま、これまでも読んでいただいている皆様、今後とも本ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
Facebookの告知ページがありますので、フォローやいいね!をしていただけますと、ブックマーク代わりになります。
証券アナリストジャーナルに関するものや、その他の私のアウトプットについての告知を追うことが可能です!
ありがとうございます!
- 投稿タグ
- 証券アナリストジャーナル