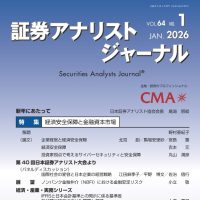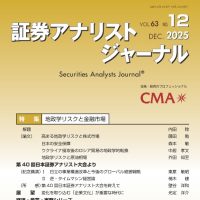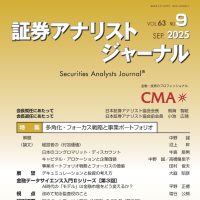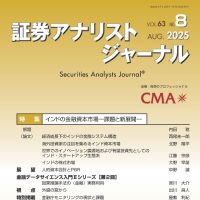やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『海外の新興運用業者促進制度(EMP)の状況とわが国の資産運用業界への示唆』という特集です。
やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『海外の新興運用業者促進制度(EMP)の状況とわが国の資産運用業界への示唆』という特集です。
長い特集のタイトルですが、「新興運用業者促進制度(EMP)」というワードが初見である方も多いのではないでしょうか?
雑誌冒頭にある「解題」が解きほぐしてくれていますので、その内容も含め、こちらに少し書こうと思います。
2023年12月、資産運用立国の実現に向けた政策プランが作成されました。
核となるテーマが3つ、①資産所得倍増プラン(2022年11月)、②コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム(2023年4月)、③資産運用業・アセットオーナーシップ改革(今般策定)があり、5分野の計画のうちの1つである「資産運用業の改革」の中に、「新興運用業者促進プログラム(日本版EMP、Emerging Managers Program)の策定・実施」というものが入っています。
EMPについて、金融庁作成の概要のPDFには以下のように書かれています。
・ 金融機関に、新興運用業者の積極的な活用や、単に業歴が短いことのみによって排除しないことを要請。金融機関等の取組事例を把握・公表。
・ アセットオーナー・プリンシプル(後述)において、受益者の最善の利益を勘案しつつ誠実かつ公正に業務を遂行する観点から、運用委託先の選定における新興運用業者の取扱いについて盛り込む。
・ 官民連携の下で、金融機関・アセットオーナーに新興運用業者を一覧化したリスト(エントリーリスト)を提供
・ 新興運用業者がミドル・バックオフィス業務を外部委託すること等により、運用に専念できるよう規制緩和を実施
日本における資産運用の歴史は、販売会社が強力であり、「ケイレツ」の資産運用会社は、資産運用のスキルアップというよりも、売れる商品の組成に勤しんできました。
情弱ビジネスと言うのは言い過ぎかもしれませんが、私たち投資家は販売会社の勧める「ケイレツ」が作った投資信託を盲目的に購入してきました。
結果、「ケイレツ」の資産運用スキルはグローバルで周回遅れとなり、投資信託を組成するたびに海外の運用機関から「スキルを買う」という残念な状況も発生しています。
『「ケイレツ」の資産運用スキルの向上は期待できない・・・。』、『EM(新興運用業者)に期待するしかない・・・。』という状況なのでしょうか。
さて、5分野の計画を今一度見てみると、「日本版EMP」とあります。海外のEMP制度を輸入するのでしょうか。
何はともあれですが、今月も、楽しみながら読み進めたいと思います!
1本目の論文は『資産運用の高度化と新興運用業者の役割―新興運用業者促進プログラム(EMP)の意義と展望―(河北博光氏)』です。
『日本が「資産運用立国」として持続的経済成長を目指す中で、アセット・オーナー・プリンシプル(AOP)と新興運用業者促進プログラム(EMP)の導入は不可欠である』とアブストラクトに書いてあります。
まず、アセット・オーナー・プリンシプル(AOP)についてですが、前段で書いた5分野の計画のうちの1つである「アセットオーナーシップの改革」の中に、「アセットオーナー・プリンシプルの策定(2024年夏目途)」というものが入っています。5つの原則があり、1行ずつにすると以下のようになります。
原則1:アセットオーナーは受益者の利益を考慮し、明確な運用目的・目標・方針を定め、環境変化に応じて見直すべきである。
原則2:運用目標に沿って専門知見を活用し、必要な体制整備や外部専門家の活用を行うべきである。
原則3:受益者の利益を最優先に、適切な運用方法とリスク管理を行い、委託先を選定・定期的に見直すべきである。
原則4:運用状況を可視化し、ステークホルダーへの説明責任と建設的な対話を行うべきである。
原則5:スチュワードシップ活動を通じ、投資先企業の持続的成長に貢献する工夫を行うべきである。
こんな原則が無くてもアセットオーナーは自主的に高みを目指すべきなんだろうけれども、私たち投資家が声をあげなかったからアセットオーナーは胡坐をかいていたということもあるでしょう。
誰の責任と言うのはさておき、今回AOPを導入することでアセットオーナーの責任ある投資行動が促進されるということなので、良きことかと思います。
次に、新興運用業者促進プログラム(EMP)ですが、大手のアセットオーナーがEM(Emerging Managers、新興運用業者)に対して積極的に資金を配分する取り組みです。
特に米国において発展してきた制度だそうで、少なくない額がEMに投じられてきたことが書いてあります。
日本でもEMPを制定してEMを育てていこうという動きです。こちらも良きことかと思います。
少し話が横道に逸れますが、私は証券会社でトレーダーをしていて、ヘッジファンドへの移籍話というのがたまにありました。
そのとき、必ず話すのが「トラックレコード」の話です。
ここ3年でトータルでナンボ儲けたとか、どういったストラテジーでナンボ儲けたとか、そんな話です。
EMにおいても「トラックレコード」は大きなポイントになりそうで、上述の金融庁作成のPDFに「単に業歴が短いことのみによって排除しない」と書いてあるのは、「トラックレコード」の問題を乗り越えるためにあえて書いた文言なのだろうと感じました。
2本目の論文は『海外のEMP事例:EMPは救済にあらず―運用者の多様化は収益力の源―(三井千絵氏)』です。
海外のEMP事例を知るのに大変有益な論文です。
1つ目の例として、ニューヨーク市の退職年金制度が紹介されていて、MWBE(Minority and Woman-owned Business Enterprises)とEMによる運用を増やすことに取り組んでいるとあります。2023年6月現在で、MWBEマネジャーに195億ドル(全体の7.71%)、EMに98.5億ドル(全体の3.85%)が配分されているそうです。
「市場の変動や経済の変化に対する年金基金の回復力を強化する」といった文言があり、多様性によってトータルリスクを抑えるような狙いがあるのではないかと推察されます。
2つ目の例として、メリーランド州の退職年金制度が紹介されています。2007年に独自のEMPを導入し、2024年度にEMPプロジェクトを拡大すると発表したそうです。2023年度の年次報告書によると、運用資産残高652億ドルのうち、EMP(改め、テラ・マリアと言うそう)は公開市場で24億ドル、MWBEのマネージャー育成に16億3000万ドルを割り当てているそうです。
他にも、独自のEMPを展開する「ユニジェスチョン(Unigestion)」や、マサチューセッツ工科大学(MIT)のエンダウメントファンドなどの事例が紹介されていて、大変参考になりました。
3本目の論文は『海外でEMPを受けて成功した運用会社の視点から(ドリュー・エドワーズ/菊地史絵氏)』です。
海外でEMPによってEM(Emerging Managers、新興運用業者)がどのように成功したかを知るのに大変有益な論文です。
1つ目の例として、「Cartica Management, LLC」が紹介されています。2007年に設立された新興国株式アクティビスト・ファンドで、創業メンバーは世界銀行グループの会社の元職員など4名。CalPERSからのEMPを通じたアンカー出資によって始まったそうで、運用資産額2億ドルで創業、2019年にかけて約32億ドルに拡大したそうです。
2つ目の例として、「Boston Common Asset Management、LLC」が紹介されています。2003年に創設されたグローバル株式を中心とするESGインテグレーション運用で知られる独立系資産運用会社だそうです。こちらは大手運用会社から独立した際にもともとの顧客をほぼ引き継ぐ形で運用資産額2億ドルでスタートし、2024年には約45億ドルに達しているとありました。
他にも、Vista Equity Partnersが紹介されています。こちらは巨大なファンドに成長しています。
4本目の論文は『EMPを運営するアセットオーナーの視点から―米国EMP担当者へのインタビューを通じて―(辻本臣哉氏)』です。
2本目の論文とともに、海外のEMP事例を知るのに大変有益な論文です。
元・米国カルフォルニア州職員退職年金基金(CalPERS)の方や、現・米国テキサス州教職員退職年金基金(TRS)の方にインタビューを行っています。
日本にEMPという仕組みを導入するにあたり、頼れるのは既にEMPを運営している方の意見でしょう。本当に貴重なものだと思います。
CalPERSはEMPに30年以上の歴史を持っていて、TRSは20年の歴史を持っているそうです!EMPを導入したときの話から継続して運営している時の話まで、非常に貴重なノウハウがこのインタビューに記されています。
また、インタビューの中で「EMPの採用期間であるが、採用したEMを1年で解約するようなことはない。だいたい3~5年が多く、最低3年は解約しない。10年という超長期のところもある。」といった発言がありました。これは、EMにとって勇気づけられるもので、やはり生の声の大切さを改めて感じました。
読了後のひとこと
今月号の証券アナリストジャーナルは、『海外の新興運用業者促進制度(EMP)の状況とわが国の資産運用業界への示唆』という特集でした。
かなり狭い分野にフォーカスした特集でしたが、興味深く4本の論文を味わうことができました。
4本の論文を読む前には、EMPが根本の解決策ではなく対症療法のような解決策なのではないかと思い、「本当にワークするのか?」という見方を持ちましたが、4本の論文を読み終えて、EMPは米国で長年の歴史があり、実際にワークしていることなど、多くのことを知り、日本における資産運用業のスキルを向上させる可能性がある施策であることが分かりました。
私は2017年にトレーダーを引退し、資産運用について外野の目線で見ています。たまに、「資産運用やってみませんか?」と言われることもありますが。笑
今の私の興味は、単純にお金を増やすことではなく、社会的インパクトについて考えたり、市場と社会の分断について考察したりすることなので、EMをやってみるといったことはおそらくないのですが、資産運用を極めたいという志を持った方には、EMPという制度は非常にサポーティブなものになるでしょう。有効な形で成長するように願うばかりです!
ということで、今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!
はじめてこの記事を見ていただいた方に
はじめまして!金融教育家のやすべえと申します。
私は、大学卒業後、証券会社3社にて金融商品のトレーダーとして20年近く勤務し、2018年から金融教育家として活動を開始しました。
詳しい説明はコチラにありますので、ぜひご覧くださいませ!
「証券アナリストジャーナル」とは、日本証券アナリスト協会が発行する会員向け月刊機関誌です。
私は、2002年に証券アナリスト検定会員となり、本誌を読み始めまして、2017年から本ブログに読んだ感想をしたためるようになりました。
「備忘録」でもあり、「書きなぐり」に近いものです。その点、ご容赦頂ければ幸いです。
ただ、証券アナリストジャーナルに寄稿してくださる方に敬意を持つこと、ブログの読者に誤解を与えずに私の思っていることをお伝えしようと心に留めながら書いています。
また、タイトル名と著者名のリンクをクリックすると日本証券アナリスト協会のサイトにジャンプし、本文の1ページ目を無料で読むことが可能です。有料で全文を購入することも可能です。
はじめましての皆さま、これまでも読んでいただいている皆様、今後とも本ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
Facebookの告知ページがありますので、フォローやいいね!をしていただけますと、ブックマーク代わりになります。
証券アナリストジャーナルに関するものや、その他の私のアウトプットについての告知を追うことが可能です!
ありがとうございます!
- 投稿タグ
- 証券アナリストジャーナル