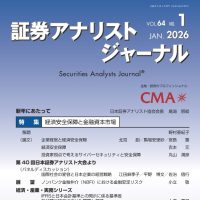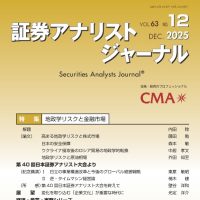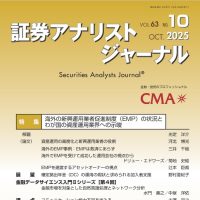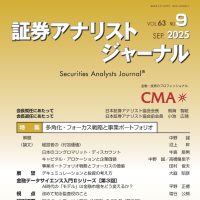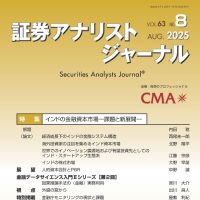やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『社会科学としての個人の資産運用』という特集です。
やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『社会科学としての個人の資産運用』という特集です。
社会科学とは、社会現象を実証的方法によって分析し、その客観的法則を明らかにしようとする学問の総称ということですが、今月の特集は実証分析によって個人の資産運用についてを解き明かしてくれそうです。
今月も、楽しみながら読み進めたいと思います!
1本目の論文は『ライフサイクルを通じた貯蓄と資産形成の理論と現実(祝迫得夫氏)』です。
題名にある通り、「理論と現実の違い」について書かれている興味深い論文でした。
最も興味深かった点は、いわゆる「リスク資産ゼロ世帯」についての考察です。「米国のようなリスク資産比率の高い国でも、リスク資産を全く保有しない家計が一定割合存在する」という事実が書かれています。
少し読み進めると、「株式保有の有無は年齢とともに山形のパターンをたどるが、株式をすでに保有している個人のグループに限定すると、リスク資産比率と年齢の間に明確な関係はない」と書かれていて、つまり、年齢グループごとの「リスク資産ゼロ世帯」が多いか少ないかという問題になるというものです。
解題を書かれている大庭昭彦さんは「個人の投資推進のための国の行うべき施策は、すでに投資に参加している個人向けよりも、まだ投資に参加していない個人向けのものが重要になるはずだという重要な主張をされている」としていて、私は本論文と解題を行き来しながら大きく頷いておりました。
2本目の論文は『長寿社会における望ましい資産管理・運用支援政策―加齢に伴う資産管理・運用能力の変化の視点から―(駒村康平氏)』です。
長寿は喜ばしいことですが、資産管理・運用を考えると不安が出てくるのではないでしょうか?
「多くの人が75歳以降、15~20年近くにわたって資産管理・運用をする必要がある」、「公的年金のモデル年金所得代替率は現在の61.2%から2050年半ばには50.4%まで、おおよそ18%ほど低下すると見込まれている」、「医療保険・介護保険でも改革が進んでいる」、「他方、加齢に伴う認知機能の低下は多くの人にとっても避けがたいものである」といった記述を見ていると、不安を感じざるを得ません。
この不安にどのように対峙するかですが、もちろん事実の正しい理解と自分なりの解釈が必要なのですけれども、お金だけが解決する問題ではないかなと正直な意見として思いました。
筆者の提案として「70歳以降、割り増しの年金を受け取ることで、高齢期における生活費の確保が可能」、「一方で、引退から年金受給開始期間は認知機能がある程度維持できているため、就労の継続や私的年金、個人金融資産の取り崩しなどで生活費を確保するようにすべき」とあり、たしかにその通りだなと思うところですが、健康を維持している高齢者の生活を学び、実践してみるというのも一つの対峙の方法ではないでしょうか?
自給自足の生活を周りの方々と取り組んだり、その中で発酵食品を作って食べて腸内環境を整えたり、知的な活動を継続して行ったり、いろいろと挑戦できることがあるでしょう。僕はまだ50代手前ですが、今のうちからそのあたりを頑張っていきたいと思っています!
3本目の論文は『個人の性格と投資に対する態度について(山根承子氏)』です。
本論文では「Big Five」と呼ばれる性格測定と投資行動についての関係を議論しています。
検索すると色々出てきますが、Wikipedia(英語)では、Openness(開放性、創造性とも)、Conscientiousness(誠実性、勤勉性とも)、Extraversion(外向性)、Agreeableness(協調性)、Neuroticism(神経症傾向、情動性とも)の5つの因子があると出てきます。例えばこちらのサイトですと120問の質問に答えて診断できるようです。
私がやってみたところ、勤勉性が高いと出ました。毎月、証券アナリストジャーナルを読んでまとめているので、当たっている気がします。(笑)
4本目の論文は『投資者の「不安感」に関する実証的分析―投資者意識調査からの検証―(青山直子氏)』です。
投資信託協会が実施している投資に関するWeb調査(投資に関する1万人アンケート)というのがあります。
本論文は、その結果に対し、「不安感」に注目して分析を行っています。
アンケートをやってみた(or読んでみた)上で論文を読むと理解度が増すかと思いますので、ぜひやってみてください!
1つ、興味深い問題を引用します。
Q. あなたが投資(株粋・投資信託)をする際に、大切だと思うことは何ですか。1番目から4番目までお選びください。
1 投資した資金が爆発的に増えること
2 投資した資金が安定的に増えること
3 投資を通じて社会全体が良くなること
4 投資を通じて投資先が成長すること
5 投資を通じて社会勉強できること
6 口座開設など初期手続きが簡単なこと
7 日々、市場動向を見ながら売買しやすいこと
8 取引画面が見やすい・操作しやすいこと
9 金融機関の担当者との人付き合い
10 周りの人と同じような商品を保有すること
11 ポイントがたまったりキャンペーン対象となること
12 手数料が安いこと
13 分かりやすい商品であること
14 小口でも投資できること
なかなか良い質問だと思いませんか!?
さて、本論文の内容を拾っていきますと、不安感が弱い投資家は積立投資やリスク資産が多いポートフォリオを選択し、リスク許容度も高い傾向があるのに対し、不安感が強い人々は定期預金や債券を保有し、リターンの認識も非現実的である傾向が見られるようです。何となく想像がつくでしょうか。
また、1本目の論文のような示唆をするならば、「不安感が強い人々、金融知識に自信のない人々に対し、金融商品を購入するときに現実的なリスク・リターン情報を提示することや、金融商品を購入する前に金融経済・投資教育を実行することが重要になる」と言えるかなと思いました。
読了後のひとこと
今月号の証券アナリストジャーナルは、『社会科学としての個人の資産運用』という特集でした。
実際に資産運用を始めるとなると、「知識面」、「精神面」、「実務面」で様々な事柄を理解する必要があります。
「知識面」では、株式・債券・不動産といった主要資産とその詰め合わせである投資信託の特徴について、金利やインフレの理解、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を含めた税の仕組み、経済指標やマーケットのルールについてなど、多岐にわたります。
「精神面」では、長期的な視点を持つこと、資産運用の目的を明確化させること、行動経済学で学ぶような群集心理や損失回避バイアスといった陥りがちな感情のブレの制御といった事象があります。
「実務面」では、入出金から金融商品購入や売却の手続きの理解、定期的なポートフォリオのチェックといったところがありますでしょうか。
これらを整理して理解しないと、モヤモヤっとした理解になります。
ポイントとして、資産運用を始める前にそのモヤモヤを完全に取り除くことが難しい点があります。やってみないと分からないところがあるからです。
やってみて分かったことを踏まえて、学ぶことが必要であると考えています。
「事前の学びと事後の学びを通じて、モヤモヤを完全に解消し、自信を持って資産運用を行うことが出来るというのが理想論」となります。
ただもちろん、すべての人がモヤモヤを完全に解消して資産運用を行うことが出来ることは現実的にあり得ないので、定期的に金融教育を受ける機会を作ることや、購入時に最低限の説明に加えて追加の情報サポートを得る機会を作ることが、問題解決に大切になってくるのではないでしょうか。購入時の追加の情報サポートをするウェブサイトがあったらいいかもなぁ・・・。
こんなことを考えさせてくれる素晴らしい4本の論文でした。著者のみなさまに感謝を申し上げます。
また、読者のみなさま、今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!
はじめてこの記事を見ていただいた方に
はじめまして!金融教育家のやすべえと申します。
私は、大学卒業後、証券会社3社にて金融商品のトレーダーとして20年近く勤務し、2018年から金融教育家として活動を開始しました。
詳しい説明はコチラにありますので、ぜひご覧くださいませ!
「証券アナリストジャーナル」とは、日本証券アナリスト協会が発行する会員向け月刊機関誌です。
私は、2002年に証券アナリスト検定会員となり、本誌を読み始めまして、2017年から本ブログに読んだ感想をしたためるようになりました。
「備忘録」でもあり、「書きなぐり」に近いものです。その点、ご容赦頂ければ幸いです。
ただ、証券アナリストジャーナルに寄稿してくださる方に敬意を持つこと、ブログの読者に誤解を与えずに私の思っていることをお伝えしようと心に留めながら書いています。
また、タイトル名と著者名のリンクをクリックすると日本証券アナリスト協会のサイトにジャンプし、本文の1ページ目を無料で読むことが可能です。有料で全文を購入することも可能です。
はじめましての皆さま、これまでも読んでいただいている皆様、今後とも本ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
Facebookの告知ページがありますので、フォローやいいね!をしていただけますと、ブックマーク代わりになります。
証券アナリストジャーナルに関するものや、その他の私のアウトプットについての告知を追うことが可能です!
ありがとうございます!
- 投稿タグ
- 証券アナリストジャーナル