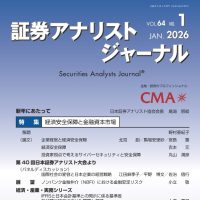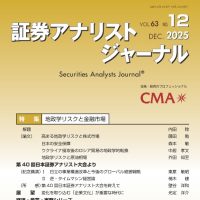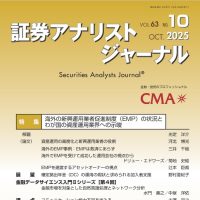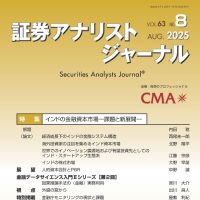やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『多角化・フォーカス戦略と事業ポートフォリオ』という特集です。
やすべえです。今月の証券アナリストジャーナルは『多角化・フォーカス戦略と事業ポートフォリオ』という特集です。
さて、ほとんどの企業は1つのビジネスからスタートしていると思います。
そして、1つ目のビジネスが成功したときに、経営者は、「2つ目、3つ目とビジネスを拡大していく多角化戦略を取る」のか、「1つ目のビジネスに集中するフォーカス戦略を取る」のか、選択するでしょう。
その選択は、すべての企業でベストの選択が出来ているわけではなく、当時ベストであった選択でさえも年月を経てベストではない選択に変化してしまうでしょう。
そういった面で、多角化戦略を取る企業は常にベストの事業ポートフォリオを模索/選択することを求められるのかもしれません。
一方、投資家は、自分で投資先を選択できる以上、多角化戦略よりもフォーカス戦略を好むと言われています。
だから、「コングロマリットディスカウント(多角化ディスカウント)が存在するんだよ。」と習いました。
「なるほど・・・」と頷きつつも、川上から川下までを手掛ける多角化でプレミアム評価されている企業があったり、3つの事業を手掛けそれら事業がお互いに売り上げや利益のブレを補完してプレミアム評価に繋がっている企業があったりと、投資家にとってシンプルに結論を出していない事象であるとも思います。
上記のような私の認識は今月の特集を読み終えて、どのように進化・変化していくでしょうか?
今月も、楽しみながら読み進めたいと思います!
1本目の論文は『経営者の〈付加価値〉―多角化企業における経営者の役割―(沼上幹氏)』です。
本論文、経営者の付加価値を考えるために、まずは付加価値そのものについて考察することからはじまります。
例えば部品の供給メーカーと完成品メーカーの取引を考えてみよう。ある部品メーカーがなくなっても、自社内製化や他メーカーからの調達で同等品を簡単に入手できるなら、このシステムから価値は消失しない。この場合、部品メーカーに〈付加価値〉はないということになる。〈付加価値〉がないのだから、部品供給メーカーは超過利潤を一切受け取れない。
この議論を経営者の付加価値に置き換えていきます。
同様に、投資家と経営者の間の分業システムに注目して経営者の〈付加価値〉を考えることも可能であろう。ある経営者がいなくても、他にいくらでも代替可能な経営者が存在していたり、投資家が直接関与したりすることで、企業価値を高められるのであれば、その経営者の〈付加価値〉は存在しないことになる。
この議論ですが、私はトレーダーの時に同じことを考えていました。
「自分の代わりがいるのか?」ということと、「自分の代わりがいるのであれば、代わりの人を起用するコストはいくらなのか?」ということです。
トレーダーとしてのスキル向上はもちろんですが、ポジショニング戦略を考えて、自分の価値をより高めようとしていました。さておき・・・。
この後、多角化企業における経営者の役割の話に移っていきます。
1970年代は「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」が用いられる全盛期だったようです。MBAの講義でも学ぶ内容ですが、「SBU(戦略事業単位)」ごとに市場シェアと市場成長率を考えて、「問題児」、「スター(花形)」、「金のなる木」、「負け犬」と判断して、投資する/撤退するといった方向性を考えるというものです。
SBU間のシナジーを考えていないのであれば、経営者の付加価値は少ないという議論です。
次に「キャピタル・アロケーション」について議論されています。内部資本市場のマネージが出来れば、外部資本市場の利用のみよりも付加価値があるという考え方です。
しかし、ディスクロージャーが進展すると外部のアナリストの判断力が高まるので、こちらも経営者の付加価値は少ないとなります。
ここではキャプランとノートンのバランスト・スコアカードの戦略マップが出てきます。財務/顧客/プロセス/学習と成長の4階層で可視化していくものですが、久々に見ました。
これを使いこなすのはとても難しいと思いますが、戦略を考えるうえで有用なツールではないでしょうか!
その次に「逆U字型曲線」について議論されます。ある程度の多角化であれば、経営者の付加価値が実現しやすいというものです。これはかなり抽象的なものであり、後で具体的な例が出てきます。
「ハードウェアxソフトウェア」という多角化に成功したアップル、「Lumada」と「OT(オペレーション・テクノロジー)xITxプロダクト」という多角化に成功した日立製作所が例として載っていました。
このあたりの文章で、「ハードウェアxソフトウェア」という多角化に成功したアップルが1つの事業である指摘することもあると書いてありました。
これはなるほどと思うところで、例えば、ファーストリテイリングが行うような「商品の企画x製造x販売」というSPAモデルは、今は1つの事業であると感じますが、1つの事業と感じる前には、3事業の多角化と感じていたのではないでしょうか?
ビジネスのくくり方の再定義が多角化のゴールであるように感じました。
2本目の論文は『日本のコングロマリット・ディスカウント―25年間の軌跡―(牛島辰男氏)』です。
日本のコングロマリット・ディスカウントについて、事実とデータに基づいて書かれています。「はじめに」にある、本稿の主要なポイント(3点)が理解を深めるうえでありがたいものでした。
①日本でもコングマリット・ディスカウントが存在、25年間を通じた平均は10%程度
②観測されるディスカウントの大きさは分析期間を通じて一定ではなく時期によって大きく変化、資本市場環境が良好で企業が外部資金を調達しやすい時に大きくなる
③日本におけるコングロマリット・ディスカウントは、非製造業企業で顕著
①はともかくとして、②は外部資金を調達しにくい時に、コングロマリットの事業群が売り上げや利益のリスク(不確実性)を下げていることが評価されていると考えられ、③は非製造業企業が1本目の論文で書いた「ビジネスのくくり方の再定義」が出来ていないと考えました。これは、規制などの影響が大きいのかもしれません。
3本目の論文は『キャピタル・アロケーションと企業価値―セグメント会計情報を用いた分析―(中野誠/高橋優里子氏)』です。
多角化企業の資本配分が企業価値(PBR)に与える影響について、「セグメント内での資源配分柔軟性(DIR)」と、「セグメント間の資源配分柔軟性(CAI)」という2つの指標を使って分析しています。
2つの指標が高い場合に企業価値が向上するという結論で「なるほど」という感じではあるのですが、CAPEXが大きくなる業界は基本的には成長性があり、そういった業界に属する企業はこれら2つの指標が高くなる傾向がおそらくあるので、CAPEXの大小で企業価値(PBR)に影響があるだけだと考えてしまったり、つまり、DIRやCAI以外のファクターの方が影響力があるのではないかと考えながら読みました。
また、本論文の1章に書いてある「キャピタル・アロケーションの実践」というのも、企業価値(PBR)に対して直接的な影響力があるのではないかと思いました。
本論文では、「キャピタル・アロケーション」について3ステップで実行する方法が紹介されています。
それぞれ、「利用可能な資金額の予測」→「事業への資金配分額の決定」→「外部資金調達・ペイアウトの決定」というものです。
これは、将来の資金配分によってCFが変わるため、エクセルのソルバーで解くようなイメージですが、これは企業の財務戦略として非常に重要な事項で、これをやっている企業とやっていない企業では財務戦略の納得性に大きな差が出るでしょう。また結果的に、「DIR」と「CAI」が高まるでしょう。
「キャピタル・アロケーションをロジカルに実践している企業は企業価値(PBR)が高い」ということを検証出来るでしょうか・・・?
何はともあれですが、読んでワクワクするような論文でした!
4本目の論文は『事業ポートフォリオ戦略とフォーカスの価値(田村俊夫氏)』です。
本論文には、「近年の日本企業の事業分離の動き」という表と、「欧米企業のスピンオフ事例」という表が出ているのですが、それだけ見ていても非常に面白いです。
これらのケーススタディによっても、多角化のメリットとデメリット、特にスピンオフの価値創造効果が見えてきます。
「ベストオーナー原則」という、いわゆるシナジー創出力が企業価値を創造するという考え方があります。
「ベストオーナー原則」の文脈でよく出てくるワードとして「スケールメリット」というのがありますが、これはフォーカス戦略での正解にすぎないと思いました。
多角化戦略での正解は「ビジネスのくくり方の再定義」ではないでしょうか?
アップルや日立製作所の戦略に感じるところがありますし、ジャーナルで言及されていない企業では、最近の業績はイマイチかもしれませんが、ニデックの戦略にこういった方向性を感じます。
メガバンクが進めている「銀・信・証の連携」も方向性的にはアリなのでしょうが、なかなかゴールが見えていないところです。
事業ポートフォリオ戦略、簡単ではないと改めて思いました。
読了後のひとこと
今月号の証券アナリストジャーナルは、『多角化・フォーカス戦略と事業ポートフォリオ』という特集でした。
4本の論文を読了したあとの、私の「企業が多角化・フォーカス戦略をどうすべきか?」に対する答えは、
①経営者が無策であれば、投資家はフォーカス戦略を求めるので、スピンオフなどで事業を売却して、コングロマリットディスカウント分の企業価値を回復させる
②経営者に卓越した多角化のアイディアがあれば、投資家がフォーカス戦略を求めても棄却し、卓越した多角化戦略を進めて、飛躍的に企業価値を向上させる
という2択でした。
個人投資家は見守るしかないかもしれませんが、エンゲージメントのできる機関投資家は経営者の多角化・フォーカス戦略をしっかりと吟味する必要があります。
アクティブ投資家のファンドマネージャーで、この辺りの目利きがあると、卓越した成績が出せそうです。なんか良いファンドありますかね!?笑
何はともあれですが、今月も最後までお読みくださいまして、ありがとうございました!
はじめてこの記事を見ていただいた方に
はじめまして!金融教育家のやすべえと申します。
私は、大学卒業後、証券会社3社にて金融商品のトレーダーとして20年近く勤務し、2018年から金融教育家として活動を開始しました。
詳しい説明はコチラにありますので、ぜひご覧くださいませ!
「証券アナリストジャーナル」とは、日本証券アナリスト協会が発行する会員向け月刊機関誌です。
私は、2002年に証券アナリスト検定会員となり、本誌を読み始めまして、2017年から本ブログに読んだ感想をしたためるようになりました。
「備忘録」でもあり、「書きなぐり」に近いものです。その点、ご容赦頂ければ幸いです。
ただ、証券アナリストジャーナルに寄稿してくださる方に敬意を持つこと、ブログの読者に誤解を与えずに私の思っていることをお伝えしようと心に留めながら書いています。
また、タイトル名と著者名のリンクをクリックすると日本証券アナリスト協会のサイトにジャンプし、本文の1ページ目を無料で読むことが可能です。有料で全文を購入することも可能です。
はじめましての皆さま、これまでも読んでいただいている皆様、今後とも本ブログをどうぞよろしくお願いいたします。
Facebookの告知ページがありますので、フォローやいいね!をしていただけますと、ブックマーク代わりになります。
証券アナリストジャーナルに関するものや、その他の私のアウトプットについての告知を追うことが可能です!
ありがとうございます!
- 投稿タグ
- 証券アナリストジャーナル